|
|
(2)高泌乳牛群における受胎率低下
|
|
|
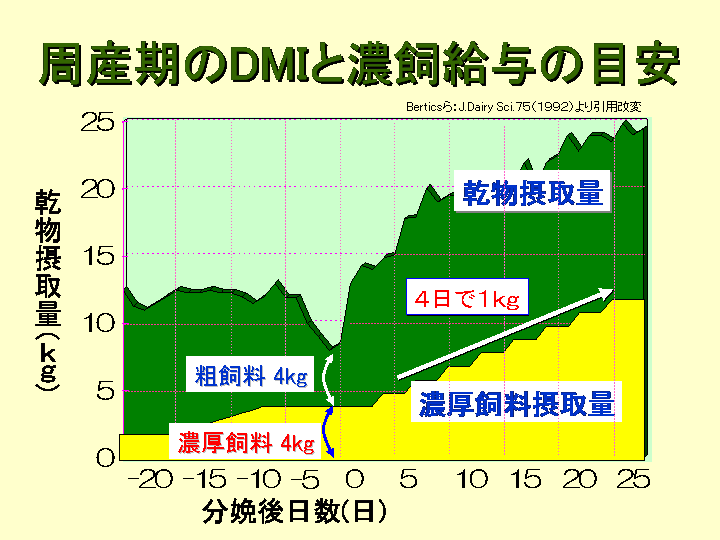
|
|
|
スライド25
|
|
|
乳牛において、これらが最も重要な周産期の飼養管理ポイントとして次のような方策が推奨されています。すなわち、分娩前の2〜3週と分娩後の3〜4週は移行期と呼ばれ、まさに乾乳期から泌乳期へと飼養管理を移行させる重要な時期です。
移行期の管理のポイントは、妊娠末期の増し飼いと泌乳期飼料への馴らし給与をかねて、濃厚飼料を増給することです。この時期の濃厚飼料給与の目安としては、乾乳前期は2kg程度与え、分娩前3週間で4kg程度まで増給し、分娩後は4日で1kgを目安に増給するというものです。
このような分娩前の馴らし給与は、ほとんどの酪農家で定着・実行されるようになり、それに伴い泌乳量も増加してきました。
ところが、乳量の増加に伴い、どうも繁殖が芳しくなくなってきているのです。
|
|
|
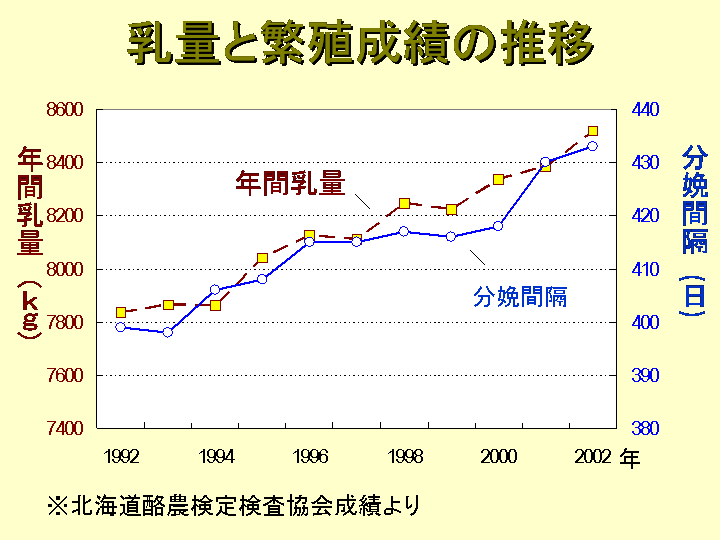
|
|
|
スライド26
|
|
|
これは、過去10余年の北海道の乳検加入農家における経産牛1頭当たり年間乳量の推移と、分娩間隔を示します。
ご覧のとおり、残念ながら乳量の伸びと分娩間隔の延長はパラレルになっています。しかも、最近もっと気になることが起きています。
|
|
|
|
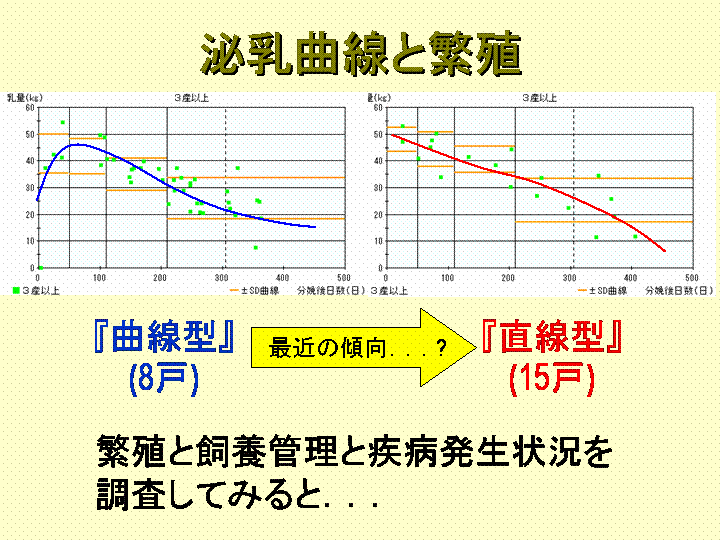
|
|
スライド27
|
|
|
従来、乳牛の泌乳曲線は、分娩後50〜100日の間にピークを形成する、まさしく山形の曲線といわれていました(曲線型)。
ところが、最近は、分娩後きわめて早期にピークを形成し、乳検の2回目検定では既に低下してしまう牛群が多くなってきました(直線型)。分娩後早期の高泌乳は『飛び出し乳量』と呼ばれ、牛の遺伝的改良により達成され、この飛び出しが高いことで年間乳量も多くなると言われています。ほんとうに、そうでしょうか・・・?
そこで、北海道内のある地域で、牛群検診を実施した23戸の農場について、検診前1年間の乳検成績から全頭の乳量を分娩後日数別に分布図を作成し、視覚的に、曲線型8戸と直線型15戸に分け、それぞれの繁殖成績と飼養管理を比較し、あわせて初回授精における受胎の有無と疾病発生との関係を調査しました。
|
|
.
|
|
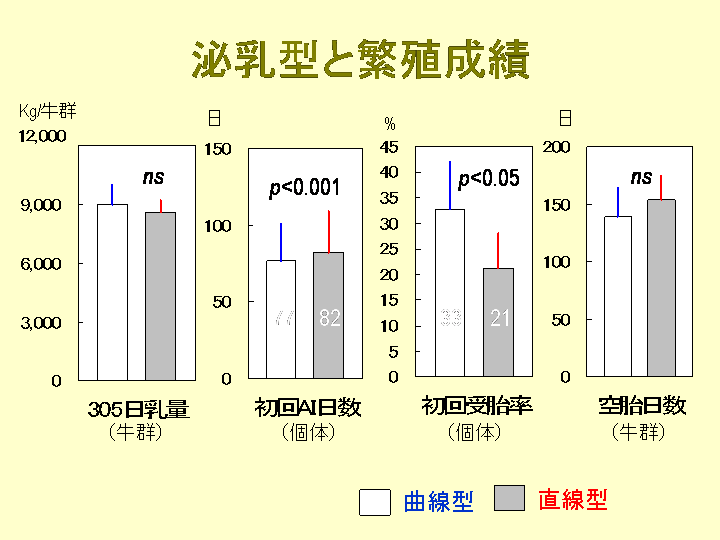
|
|
スライド28
|
|
|
その結果、305日乳量には差がありませんでしたが、直線型の牛群では、分娩〜初回授精日数が延長して初回受胎率が低く、空胎日数も延長する傾向にありました。
|
|
|
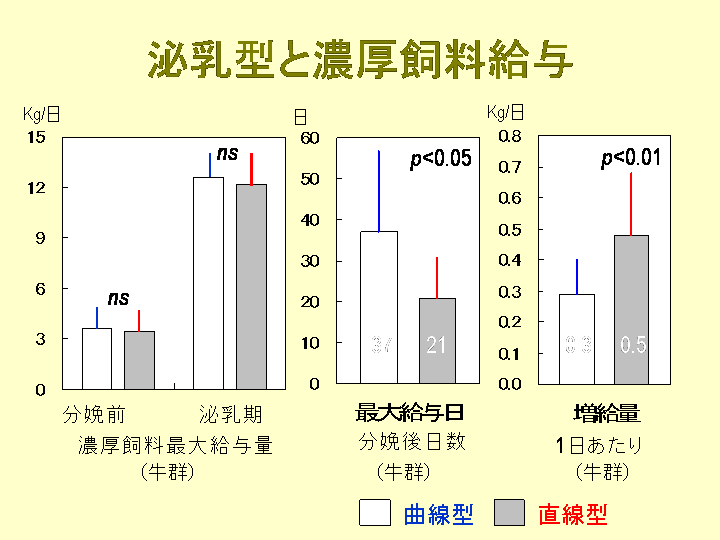
|
|
スライド29
|
|
|
飼養管理では、分娩直前の濃厚飼料給与量や泌乳期の最大給与量には差がありませんでしたが、分娩後の最大給与量到達までの日数が、曲線型牛群の平均37日に対し、直線型牛群では21日でした。これから、1日当り増給量を計算すると、曲線型が0.3kgであったのに対し、直線型では0.5kgに達していました。
|
|
|
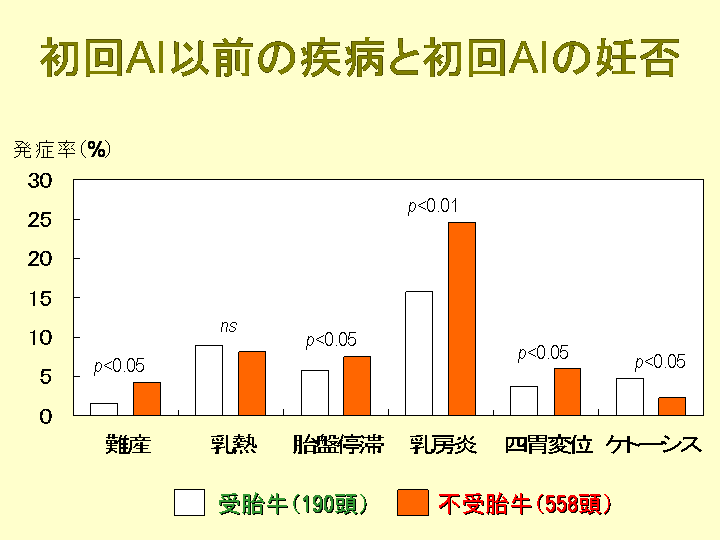
|
|
スライド30
|
|
|
また、曲線型、直線型に関係なく、初回授精で妊娠した牛(190頭)と、しなかった牛(558頭)について、授精前に獣医師によって治療を受けた診療記録を調査しました。なお、ここでは授精されなかった牛は含まれません。
その結果、不受胎牛は、受胎牛に比べ、難産、胎盤停滞、乳房炎、第四胃変位に罹ったことのあるものが有意に多く、これらの病気が初回受胎率低下の要因になっていることが確認されました。なお、乳熱発生率には差がなく、ケトーシスは、むしろ受胎牛の方が高い発生率でした。
|
|
|
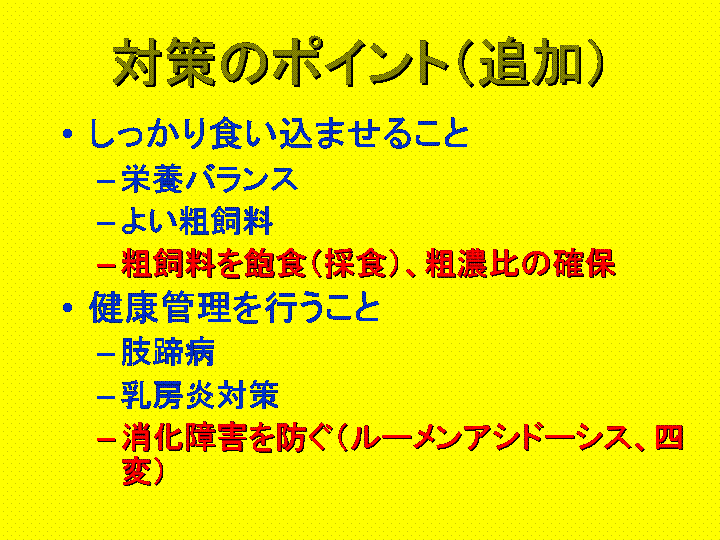
|
|
スライド31
|
|
|
以上のことから、最近の高泌乳の繁殖障害牛群では、産後の濃厚飼料給与が乱暴で、増給速度が速い。乳量は、検定1回目に最高を記録し、2回目以降は既に減少している。不受胎牛では、周産期病にかかったことのある牛が多い。すなわち、消化障害やエネルギー不足、産褥感染等の疾病ストレスにより、発情回帰が遅れて初回授精が遅くなり、受胎率も低下している。このような、シナリオがあるように思われます。
したがって、対策のポイントは、前述の対策に加え、さらに、よい粗飼料を十分に食い込ませて特に粗濃比を確保することが重要と思われます。このことにより、ルーメンアシドーシスや第四胃変位などの消化障害もまた防ぐことができます。
|